社会人になって数年が経ち、ニュースやSNSで「老後資金2,000万円問題」や「新NISA」の話題を見るたびに、不安が募っていきました。「自分も何か始めなきゃ」「貯金だけでは足りない」──そう思い立って投資を始めたのが、私の資産運用のスタートです。
しかし、当時の私は楽しむためではなく、焦りから投資を始めていたように思います。周りの同年代が次々と「資産〇〇万円達成」と投稿しているのを見ては、「自分ももっと頑張らないと」と比較ばかり。投資が「未来の安心」ではなく、「今の不安を埋める手段」になっていました。
最初のうちは、上がったり下がったりするチャートを見るのが刺激的で、ある種のスリルを感じていました。でも時間が経つにつれ、「もっと増やしたい」から「下がって怖い」へ、そして「また焦る」という無限ループに陥っていたんです。
そんな私が少しずつ変われたのは、「投資は競争ではなく、自分を整える時間なんだ」と気づいてからでした。
この記事では、投資初心者が陥りがちな「焦りの投資」から抜け出し、感情に左右されない投資習慣を築くまでの実体験をお伝えします。この記事を読むことで、投資に対する不安を減らし、自分のペースで続けられる投資スタイルを見つけるヒントが得られるかもしれません。
なお、本記事は筆者個人の体験談であり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。
投資が義務だった頃の自分
SNSと比較しては落ち込む毎日
投資を始めたばかりの頃、私はSNSで他の投資家の投稿を見るのが日課になっていました。「20代で資産1,000万円達成しました」「S&P500で年間プラス30パーセント」──そんな報告を見るたびに、自分が取り残されている気がして焦っていました。
本来は将来のために始めたはずの投資が、いつの間にか他人と比べる競争になっていたんです。結果が出ていない自分を責めては、「次こそは」と無理にリスクを取り、結局は疲れてしまう。今思えば、この時期の私は「お金を増やす」より「自分の心をすり減らす」ことに時間を使っていました。
焦りから行動がブレていた頃の自分を振り返ると、こんな特徴がありました。
値動きを1日何回もチェックする習慣がついていた。SNSで他人の成績を見て落ち込む日々が続いた。すぐに利益を求めて売買を繰り返し、長期投資と言いながら結局は短期思考に陥っていた。
今でこそ笑えますが、当時は本気で「努力してるのに成果が出ない」と思い込んでいました。でも冷静に見れば、それは投資ではなく感情の取引でした。
関連記事:積立投資だけが救いだった──焦りの投資から学んだ「ブレない運用」の大切さ
投資の目的を見失っていた
そもそも、なぜ投資を始めたのか。その目的を自分でも言葉にできていなかったことが、迷走の原因だったと考えています。
将来に備えたいのか。老後の不安を減らしたいのか。それとも、ただ周りに置いていかれたくなかっただけなのか。
明確な理由がないまま、「なんとなく増やしたい」と思っていたので、どんな結果になっても満たされませんでした。利益が出ても一瞬で不安が戻ってくるし、損失が出ると「やっぱり自分には向いていない」と落ち込む。
投資の世界では、「目的のないお金は迷う」と言われることがあります。まさにその通りで、当時の私は何のために投資をしているのかを見失っていました。
義務感だけでは続かないと気づいた瞬間
そんなある日、私が保有していた投資信託が一時的にマイナス10パーセントになったことがありました。そのとき、「自分はこの下落を冷静に見られない」と気づいたんです。
「これって本当に自分のための投資なんだろうか?」「増やすことばかり考えて、心の余裕を失ってるのでは?」
そう感じた瞬間、チャートを閉じて深呼吸しました。あのとき、初めてお金との距離を見直そうと思えた気がします。
関連記事:お金を増やすことを「楽しむ」感覚──義務感から楽しみに変わった私の投資との向き合い方
考え方が変わったきっかけ
チャートを見ない期間をつくった
義務感だけで投資を続けていた頃、私は毎日のようにチャートを開き、価格の上下で感情が乱れていました。「今日は上がった」「昨日より下がった」と、投資が数字のゲームのようになっていたんです。
そんな自分に疲れてしまい、思い切ってチャートを一切見ない1か月を過ごしてみることにしました。積立設定だけはそのままにして、日々の値動きは確認しない。
最初は落ち着かず、「今どうなっているんだろう」と気になって仕方がありませんでした。でも数週間経つと、思った以上に生活に影響がないことに気づきます。むしろ、相場を気にしない時間の方が穏やかに過ごせるようになりました。
そのとき、ようやく理解しました。「自分が相場を動かしているわけではないのに、なぜこんなに支配されていたんだろう」と。
ここで補足しておきたいのは、長期投資に関する統計データです。Investopediaによると、S&P500の1957年以降の平均リターンは名目で約10.4から10.5パーセントとされています。インフレ調整後ではもう少し低くなりますが、それでも長期ではプラス推移が多い傾向があると言われています。ただし、これは過去の実績に基づくものであり、将来を保証するものではありません。
増やすことより整えることにフォーカスした
それから私は、「どうすれば利益を増やせるか」よりも「どうすれば気持ちを整えて続けられるか」に意識を向けるようになりました。投資に限らず、仕事や生活でも、続けるためには感情の安定が欠かせません。
そこでルールを決めました。
積立設定は一度決めたら基本的に変更しない。運用確認は月1回だけにする。含み損を見ても「予定どおり下がってる」と考える。焦りを感じたら、売買せずに散歩に出る。
この小さなルールを守ることで、徐々に感情に流されない投資ができるようになりました。投資を楽しめるようになったのは、この整える習慣を持てたことが大きいと考えています。
投資理論では、インデックス投資のように長期・非頻繁売買を前提にした場合、感情に左右されにくいと言われることがあります。ただし、これはあくまで一般的な期待であり、短期で必ずリターンがあるわけではないという点に注意が必要です。
投資を自分と向き合う時間と捉えるようになった
以前は、投資をお金を増やすための手段だと考えていました。でも今では、投資は自分と向き合う時間だと感じています。
どんなリスクなら安心して持てるのか。将来、どんな生活をしたいのか。今のお金の使い方に後悔はないか。
投資を通して、こうしたことを考える時間が増えました。それは数字ではなく、自分の価値観を確認する時間です。
お金と真剣に向き合うことで、漠然とした不安が少しずつ薄れ、「自分の人生を自分で選べている」という実感が生まれました。これは私個人の体験であり、万人に当てはまるものではありませんが、投資を通じて自分自身を理解することの価値を感じています。
関連記事:20代から始める資産運用|FIREを目指す私の投資方針と実体験
楽しめる投資習慣を作るために意識していること
無理のない金額で続ける
投資を続ける上でいちばん大切なのは、続けられる金額で始めることだと考えています。最初の私は、「多く積み立てたほうが早く増えるはず」と考えて、収入ギリギリの金額を設定していました。でも数か月後、生活費が足りなくなり、結局積立を一時停止してしまいました。
そのとき気づいたのは、続けることこそが投資の最大のリターンだということです。
それ以来、私は「使わなくても気にならない金額」で設定しています。投資は体力勝負ではなく持久走だと考えられるようになりました。無理をしない設定にするだけで、長く穏やかに続けられるようになりました。
金融庁の資料でも、長期・積立・分散投資の重要性が強調されています。これは継続することで時間を味方につけるという考え方に基づいています。
関連記事:少額からでもOK!20代に最適な資産運用の始め方|月3万円から始めた私の実体験
目的を安心に置き換える
以前は「もっと増やしたい」「早く資産を作りたい」と思っていましたが、今は「お金の不安を減らすために投資している」と考えています。
目的を増やすことから安心を積み上げることに変えると、結果に一喜一憂しなくなりました。資産が増えたときは「これで少し未来が楽になるな」と思えるし、下がったときも「これも経験のひとつ」と冷静に受け止められます。
投資を生活の一部にする
投資を特別なことと思っているうちは、どこかプレッシャーを感じてしまいます。でも、家賃を払うのと同じように毎月の固定費の一部と考えると、自然と習慣化されていきます。
私の場合は、給料が入ったらまず自動で投資用口座に振り分けるよう設定しています。そうすると、残りの金額で生活するのが当たり前になり、投資を考えなくてもできることに変えられました。
習慣になったことで、投資は「やらなきゃ」ではなく「今日も積み立ててる」という小さな安心に変わりました。この無意識で続けられる仕組みが、投資を楽しむいちばんの秘訣かもしれません。
関連記事:会社員が今日からできる節約術と、それを投資に回す方法
結果より続いている自分を褒める
投資は短期間で成果が出るものではありません。だからこそ、結果ではなくプロセスを評価することを意識しています。
相場が荒れても積み立てを止めなかった。無理なリスクを取らずに続けられた。1年を通して自分のルールを守れた。
こうした小さな継続を褒めるようになってから、投資がぐっと楽しくなりました。数字よりも、「自分で決めたことを守れた」ことが自信につながる。そう思えるようになると、投資は我慢の時間ではなく自己成長の時間に変わります。
投資を通じて自分を知る
投資をしていると、自分の性格がよく分かります。リスクを取るのが怖いタイプなのか、それとも慎重すぎるタイプなのか。自分の行動パターンを観察していると、「お金の扱い方は生き方」だと感じるようになりました。
私はこの自分を知る感覚が、投資を楽しむ最大の理由です。お金の増減を超えて、「自分がどういう人間なのか」を少しずつ理解できる──それが、長く付き合うモチベーションにつながっています。
まとめ
投資が教えてくれたこと
投資を始めたころは、誰もが「早く増やしたい」と思うものです。でも続けていくうちに分かるのは、増やすことより続けられる仕組みを作ることのほうが大切だということでした。
市場の波に一喜一憂するよりも、「今月も積み立てできた」「焦らずに続けられた」といった小さな積み重ねこそ、未来の大きな安心につながると考えられるようになりました。そして何より、投資を義務から習慣に変えたとき、初めて心から楽しめるようになりました。
この記事で私が最もお伝えしたかったのは、投資は競争ではないということです。他人と比較して焦る必要はなく、自分のペースで、自分の目的に向かって進めばいい。そう思えたとき、投資は不安の種ではなく、未来への希望に変わりました。
未来の自分へ
投資は競争でも、短距離走でもありません。自分のペースで、少しずつ前へ。お金を増やす過程そのものを、ぜひ自分らしく楽しんでいきましょう。
焦りから始まった私の投資も、今では毎月の楽しみになっています。これから投資を始める方、すでに始めているけれど不安を感じている方にとって、この記事が少しでも心の支えになれば幸いです。
免責事項
投資について
本記事で紹介している投資手法や考え方は、筆者個人の経験に基づくものであり、特定の投資商品や投資手法を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。過去の統計やデータは将来の運用成果を保証するものではありません。投資判断は必ずご自身の責任で行い、必要に応じてファイナンシャルプランナーや証券会社などの専門家にご相談ください。
体験談について
本記事に記載されている投資成果や経験は、筆者個人のものであり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。これはあくまで一個人の体験であり、万人に当てはまるものではないという点をご理解ください。市場環境や個人の状況によって結果は大きく異なる可能性があります。
統計データについて
本記事で引用している統計データや一般論は、執筆時点で公開されている情報に基づいていますが、これらは過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。市場環境は常に変化しており、同様の結果が得られる保証はありません。
その他
本記事の情報は執筆時点のものであり、最新の制度や金融商品の内容とは異なる場合があります。最新情報については、金融庁や各金融機関の公式サイト、または専門家にご確認ください。
関連記事
- 20代・30代の初心者が資産運用を始める前に知っておきたい5つのこと
- 【実体験】SBI証券×三井住友カードゴールドで毎月10万円積立|ポイント還元と投資習慣を語る
- 『貯金=安心』はもう古い?インフレ時代に知っておきたい現金のリスクと対策
- お金を増やすことを「楽しむ」感覚──義務感から楽しみに変わった私の投資との向き合い方
- 投資初心者が最初の1年で陥りがちな5つの失敗──実体験から学んだ後悔しない資産形成のスタート術
参考サイト
- 金融庁「NISA特設ウェブサイト」
- 日本証券業協会「投資の時間|投資のはじめ方」
- 投資信託協会「そもそも投資信託とは?」
- Investopedia「S&P 500 Index: What It Is and How to Invest」
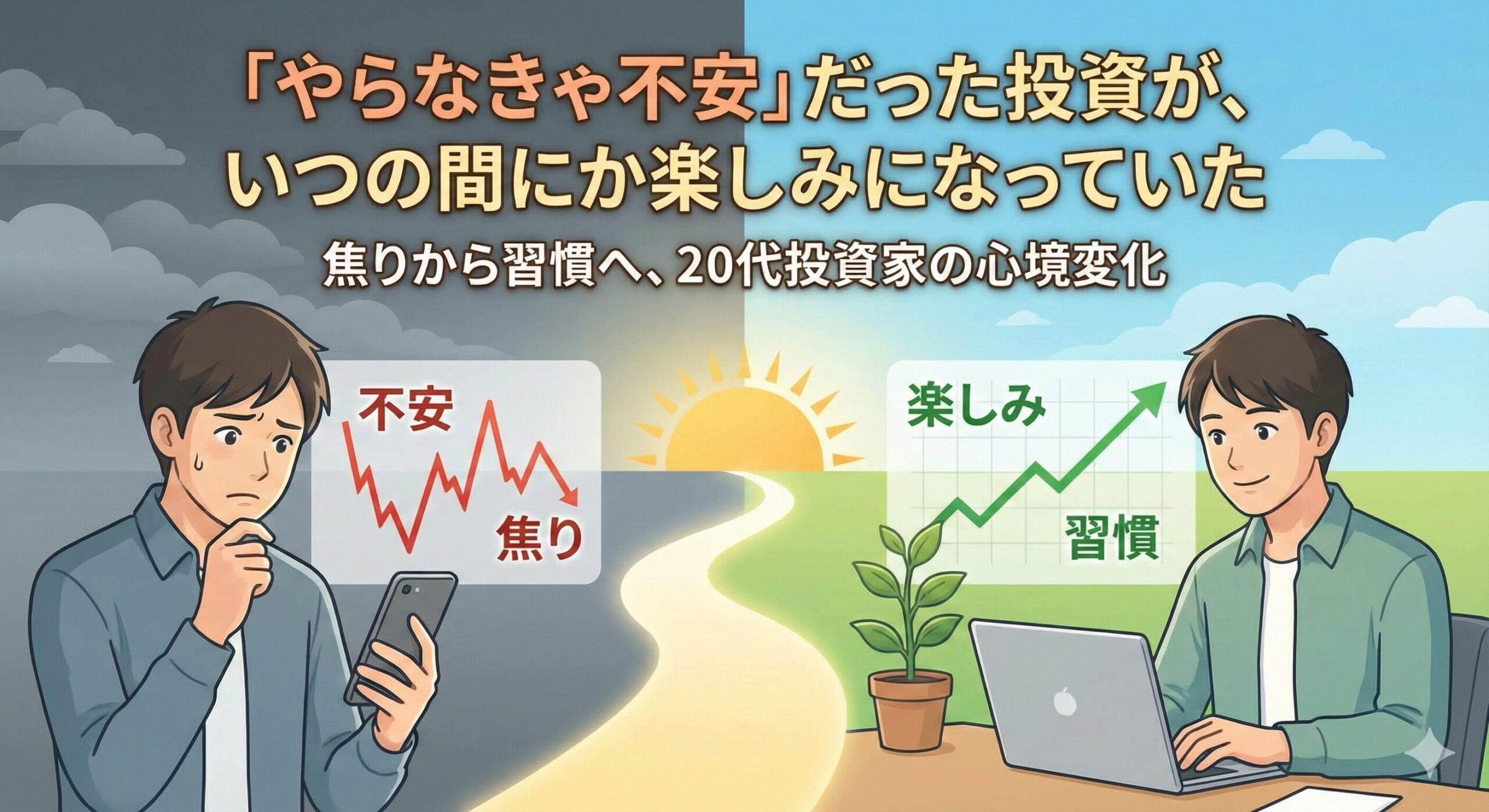



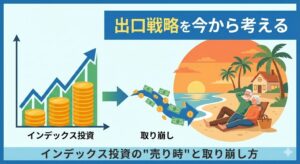


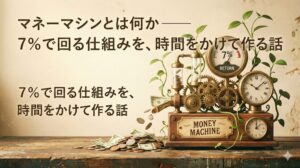
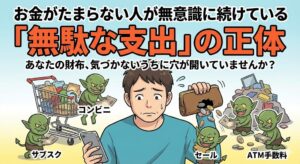

コメント