2025年秋、金(ゴールド)の国内価格がついに1グラムあたり2万円を突破しました。これは過去最高値であり、世界的に見ても「安全資産」への資金流入が加速していることを示しています。
一方で、「なぜ今、金が買われているのか?」「株やドルとの関係は?」と疑問に思う投資家も多いはずです。
私自身も投資を始めた当初、「金はリスクがない」「値動きが小さい」と誤解していました。しかし実際は、金も立派な”投資対象”であり、タイミングや目的を誤ると資産を減らすリスクもあります。
この記事では、なぜ金価格が過去最高を更新しているのか、「安全資産」と呼ばれる理由と誤解、投資家が金とどう付き合うべきかを、データと投資家目線の両面から整理していきます。
なぜ金価格は2万円を突破したのか? 背景にある3つの要因
金(ゴールド)は「安全資産」として知られていますが、2025年に入ってここまで急騰したのには、明確な3つの要因があります。
要因①: 世界的な利下げ転換とインフレ継続
アメリカ・欧州・日本を含む主要国で、2024年後半から利上げサイクルの終了→利下げ局面に入りました。
金は金利を生まない資産ですが、他の資産(金利のつく預金や債券)との相対的な魅力が高まると買われやすくなります。
加えて、エネルギー価格や人件費の上昇でインフレが根強く残っていることも金高騰の要因です。インフレ時には「通貨の価値が下がる=実物資産に逃避する」流れが起こるため、投資家がリスク分散として金を買う動きが強まりました。
参考:日本銀行「金融政策」
要因②: 世界的な地政学リスクとドル離れ
中東や東欧の情勢不安、米中対立など、地政学的な緊張が続いています。不確実性が高まると、株式や為替よりも「金」へ資金が逃避する傾向があります。
特に2025年は、各国の外貨準備においても「金保有を増やす中央銀行」が増加。インド・中国・ロシアを中心に、ドル資産から金へのシフトが進んでいます。
つまり、「金は安全資産」というよりも、「ドルのリスクヘッジ資産」として買われている側面が強いのです。
要因③: 円安と国内投資家の買い需要
日本市場では、1ドル=150円前後という歴史的円安が続いています。金はドル建てで取引されるため、円安になるほど円換算の金価格は上昇します。
たとえば、ドル建て金価格が横ばいでも、為替が5%円安になるだけで、日本円ベースでは自動的に5%値上がりする仕組みです。
加えて、「株や不動産が上がりすぎて手が出しにくい」と感じる投資家が、リスク分散として金を少額積み立てる動きも広がっています。
関連記事:ドル円150円時代の投資戦略|為替リスクと賢いアセット配置
金は本当に”安全資産”なのか?──誤解されやすい3つのポイント
「金=安全資産」という言葉はよく聞きますが、実はこの表現には誤解が多く含まれています。確かに”通貨や株式と異なる値動きをする”という意味では安全ですが、「損をしない」「常に上がる」資産ではありません。
誤解①: 金は「値動きが小さい」わけではない
金は株式より安定していると思われがちですが、実際には為替や景気サイクルの影響を大きく受ける資産です。
過去10年間のドル建て金価格を見ると、2013〜2018年には一時的に30%以上下落した局面もありました。
つまり、短期では”安全”どころか”ボラティリティ(値動きの大きさ)”が高い資産でもあります。安全とは「元本保証」ではなく、他資産と異なる動きをする=分散効果があるという意味なのです。
誤解②: 金は「インフレに強い」が「景気回復局面では弱い」
金はインフレ時に強いと言われます。実際、物価上昇で通貨価値が下がると、実物資産である金の価値が上がりやすくなります。
しかし逆に、景気が回復して金利が上昇する局面では、金の魅力が薄れ、売られやすくなる傾向があります。
たとえば、2010年代のアメリカのように株高+ドル高が進むと、「金を持つより株を買った方が得」と判断され、価格は伸びにくくなります。つまり金は”景気の逆を行く資産”であり、常に右肩上がりではありません。
関連記事:『貯金=安心』はもう古い?インフレ時代に知っておきたい現金のリスクと対策
誤解③: 金は「利息を生まない」=持ち続けるだけでは増えない
金の最大の特徴は、配当も金利も生まないことです。
そのため:
- 株のように企業成長でリターンが増えることもなく
- 債券のように利息を得ることもできません
金が上がるのは、他の資産が下がった時。つまり、「他がダメなときの保険」として機能する存在です。
したがって、資産の中心に置くのではなく、ポートフォリオの5〜10%程度を”リスク分散枠”として持つのが理想です。
金は「儲かる資産」ではなく、「守る資産」。この性質を正しく理解することで、投資全体の安定性がぐっと高まります。
投資家が知っておくべき「金投資の3つの選択肢」
金は「守りの資産」として優れていますが、投資手法によって特徴やリスクは大きく異なります。ここでは代表的な3つの方法を整理します。
選択肢①: 純金積立──少額から始められる王道スタイル
毎月1,000円など少額からコツコツ買える「純金積立」は、初心者にも人気の手法です。価格変動を平均化できるドル・コスト平均法を活用できる点が大きな魅力です。
メリット:
- 少額から始められる(証券会社や貴金属業者で口座開設が可能)
- 長期的に見ればインフレヘッジ効果が期待できる
- 定期積立のため、購入タイミングを気にする必要がない
デメリット:
- 手数料(約1〜3%)がかかる
- 実物の受け取りには別途費用が発生する
長期的なインフレ対策には向いていますが、短期の値上がり益を狙う投資には不向きです。
選択肢②: 金ETF──売買のしやすさとコストの安さが魅力
「もう少し手軽に金に投資したい」という場合は、ETF(上場投資信託)が有力な選択肢です。代表的な銘柄には「SPDRゴールドシェア(GLD)」や「国内の金価格連動型ETF(1328など)」があります。
メリット:
- 証券口座から株式と同じ感覚で取引できる
- 保管や盗難のリスクがない
- 信託報酬が低く、コストを抑えやすい
デメリット:
- 配当がなく、インカムゲインは得られない
- 為替の影響を受けやすい(円建てETFの場合)
インフレ対策やリスク分散を目的とする中級者に向いています。ポートフォリオの中で「リスクヘッジ枠」として位置づけるのが現実的です。
選択肢③: 金貨・地金──実物資産としての安心感を重視するなら
田中貴金属や三菱マテリアルなどで購入できる「金貨・地金(インゴット)」は、実物資産としての信頼性が高い方法です。
メリット:
- 実物としての安心感がある(信用リスクがない)
- 海外送金や金融制裁などの影響を受けにくい
デメリット:
- 保管・盗難リスクがある
- 売却時の手数料が高い
- 小口での取引がしづらい
「金融システムの外に資産を持ちたい」「万一に備えたい」といった目的には向いていますが、運用効率を重視するならETFや積立の方が実践的です。
参考:田中貴金属工業「金投資の基礎知識」
金をポートフォリオにどう組み込むか──「守りの資産」としての位置づけ
金は”リスクを取らないための資産”であり、株式や不動産とはまったく異なる役割を持ちます。そのため、全資産の中でどの程度の比率を金に充てるかを考えることが重要です。
金の役割は「リターンを増やす」ではなく「下落時のクッション」
株式や投資信託が順調に値上がりしているとき、金はあまり注目されません。しかし、景気後退や金融不安が起きたとき、金の存在がポートフォリオ全体を守ります。
たとえば、リーマンショックやコロナショックの際、株価が大幅に下落する一方で金価格は上昇しました。これは、投資家がリスク資産から安全資産に資金を移すためです。
つまり、金は「利益を狙う資産」ではなく「他の資産を守る資産」。株や債券の値動きと逆方向に動くことで、全体の損失を和らげるクッションのような役割を果たします。
関連記事:20代・30代のための資産配分戦略──株式・債券・オルタナティブの役割とリバランスの重要性
適切な保有比率の目安は「5〜10%」
一般的に、資産全体の5〜10%を金で保有するのが目安とされています。これは、インフレや金融ショックといった”想定外の事態”への備えとして機能します。
金を持ちすぎるとリターンの伸びを抑えてしまい、逆にまったく持たないと、市場が荒れたときにリスクを吸収できません。
- 株式中心のポートフォリオ → 金5%程度
- 債券中心のポートフォリオ → 金10%程度
- 為替や仮想通貨も含むハイリスク構成 → 金15%程度でも可
このように、リスク資産の割合が高いほど、金を厚めに組み込むのが自然です。
長期的には「安心感のポートフォリオ」を意識する
投資を続けていると、相場の上下に一喜一憂してしまうことがあります。しかし、どんな局面でも「金」という守りの資産を一定割合で保有しているだけで、心理的な安定感がまったく違ってきます。
私自身も株式中心で運用していた時期には、相場の下落に不安を感じることが多くありました。しかし、金をポートフォリオに加えてからは、急落局面でも落ち着いて判断できるようになりました。
投資の本質は「増やすこと」だけでなく、「守りながら続けること」。その意味で、金は長期投資を支える”土台の一部”と言えます。
関連記事:暴落時代を生き抜く20代の投資戦略──歴史が教える「10年後に後悔しない」資産形成
まとめ: 金投資を”終わりのない安心材料”に
2025年に入り、金価格は過去最高の1グラム=2万円台に到達しました。この背景には、利下げ局面・インフレ継続・地政学リスク・円安という複数の要因が重なっています。
金は「利益を狙う資産」ではなく「資産を守る資産」
金を買う目的は「利益を出すこと」ではなく、「安心して投資を続けること」です。資産の一部に金があるだけで、相場が下がっても慌てずに行動できます。この心理的な安定こそ、長期投資を成功させる最大の武器です。
私自身も、リスク資産の値動きに一喜一憂していた頃に比べ、ポートフォリオの一部を金に振り分けてからは、相場を”俯瞰して見られる”ようになりました。「増やす」と「守る」を両立させるバランスが取れたと感じています。
重要なポイント
- 金は「利益を狙う資産」ではなく「資産を守る資産」
- 保有比率の目安は全体の5〜10%
- 利下げ・円安・インフレ局面で長期的な価値を発揮
- 投資の安心感を支える”ポートフォリオの要”として活用する
今後も世界経済や金融政策が大きく揺れる中で、「何を持つか」よりも「どう分けるか」が資産形成の鍵になります。金はその中で、”長期的に信頼できるバランス資産”としての存在感を増しています。
免責事項
本記事は筆者の個人的な見解と一般的な投資情報に基づく情報提供を目的としており、特定の投資商品の推奨や投資勧誘を目的とするものではありません。
重要な注意事項:
投資について
- 投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります
- 投資判断は必ずご自身の責任において行い、必要に応じてファイナンシャルプランナー(FP)など金融の専門家にご相談ください
- 本記事で紹介した筆者の体験は個別の事例であり、すべての方に当てはまるものではありません
金投資について
- 金価格は為替や世界情勢によって大きく変動します
- 過去の価格推移は将来の価格を保証するものではありません
- 投資手法(純金積立、ETF、現物)にはそれぞれメリット・デメリットがあります
市場情報について
- 本記事で紹介した価格や市場動向は、執筆時点(2025年12月)のものです
- 市場環境は常に変化するため、最新の情報は各種公式サイトでご確認ください
その他
- 本記事の執筆者はファイナンシャルプランナーや金融商品取引業者ではありません
- 金投資に関する具体的な判断については、専門家にご相談されることをおすすめします
読者の皆様におかれましては、本記事の内容を参考情報の一つとして、ご自身の状況に合わせて専門家に相談のうえ、慎重に判断されることを強くおすすめします。執筆者および本サイトは、本記事の内容に基づいて読者が行った判断や行動の結果について一切の責任を負いません。
関連記事
- ドル円150円時代の投資戦略|為替リスクと賢いアセット配置
- 『貯金=安心』はもう古い?インフレ時代に知っておきたい現金のリスクと対策
- 20代・30代のための資産配分戦略──株式・債券・オルタナティブの役割とリバランスの重要性
- 暴落時代を生き抜く20代の投資戦略──歴史が教える「10年後に後悔しない」資産形成
- 暴落はギフト──積立投資が市場下落で勝てる科学的理由
参考サイト
- 日本銀行:「金融政策」
- 田中貴金属工業:「金投資の基礎知識」
- World Gold Council:「Gold Market Commentary」






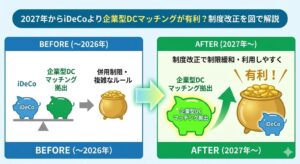



コメント