はじめに
半導体は「現代の米」とも呼ばれる、経済や社会に不可欠な存在です。
スマートフォン、パソコン、自動車、そしてAIやクラウドサービス。
私たちの生活やビジネスは、あらゆる局面で半導体によって成り立っています。
投資家にとっても半導体は外せないテーマです。
一方で、株価は循環産業の性格を色濃く反映し、短期的には激しい上下動を繰り返してきました。
「王道」ではあるものの、同時に投資家を悩ませる難しいセクターでもあります。
私はこのジレンマを、「インデックス+半導体」 という組み合わせで乗り越えるのが現実的だと考えています。
この記事では産業構造や歴史的な背景を整理しつつ、投資家としての心理的課題や、私自身の考え方を踏まえた「半導体投資との付き合い方」を詳しくお伝えします。
半導体産業の全体像
半導体産業は、単に「チップを作る」だけではなく、設計・製造・装置・材料といった細かな工程で成り立っています。
- ファブレス(設計専業):NVIDIA・AMD・Qualcomm
- ファウンドリ(受託製造):TSMC・Samsung
- 製造装置:ASML(EUV独占)・東京エレクトロン・SCREEN
- 材料:信越化学・SUMCO(シリコンウエハ大手)
- IDM(垂直統合型):Intel・Micron・TI
特にASMLがEUV露光装置を独占している事実は、投資家にとっても重要です。
「1社が世界を握る」構造は安定感を生むと同時に、リスク集中も意味するからです。
👉 外部リンク:経済産業省:半導体・デジタル産業戦略
歴史と投資家の視点
半導体業界は常に覇者が入れ替わってきました。
- 1980年代:日本企業がDRAMで世界を制覇
- 1990年代:IntelがCPU市場を独占
- 2000年代:スマホの普及でQualcommやTSMCが急成長
- 2010年代:クラウド・AIでNVIDIAが台頭
- 2020年代:米中対立、地政学リスクが顕在化
この歴史は「個別株一点集中」のリスクを物語っています。
一時的に王者となっても、技術革新の波で数年後には苦境に陥る。
インテルの苦戦はまさにその典型です。
👉 私の考え:
この歴史を踏まえると、私は「半導体=ETFで広く押さえる」のが基本だと思っています。
個別株投資は魅力的ですが、全体を見失うと痛手を負いやすいからです。
AIブームと半導体
生成AIは、半導体需要を一気に押し上げる「ゲームチェンジャー」です。
NVIDIAのGPUはもはや「金のなる木」と言える存在で、データセンター投資がNVIDIA一社に集中しているのは驚異的です。
ただし、私はこの集中をやや不安視しています。
NVIDIAは圧倒的ですが、「一社依存」の構造が続く限り、規制や競合の台頭が起きる可能性が高いと見ているからです。
実際にGoogle・Amazon・Metaなどは独自AIチップを開発しており、「脱NVIDIA」 の動きが徐々に進んでいます。
👉 出典:NVIDIA Newsroom
電力と半導体
IEAのレポートによれば、2030年の世界のデータセンター消費電力は945TWhに達し、日本の年間消費を上回るとされています。
私はこの点を「半導体=エネルギー産業でもある」と理解しています。
単にチップを作るだけでなく、電力効率の改善が半導体産業の競争力を左右する。
つまり今後の投資では、「性能×省エネ」 の両立を図れる企業に注目すべきだと考えています。
政策支援の厚さと投資判断
米国はCHIPS法で520億ドル規模、日本はTSMC熊本に7,320億円、Rapidusに最大5,900億円、EUは430億ユーロ──巨額の補助金が投入されています。
これは投資家にとって「安心材料」である一方で、私は次のように考えます。
「補助金頼みの企業はリスクも抱える」 ということです。
補助金はあくまで一時的支援であり、長期的に競争力を維持できるかは別問題だからです。
投資家の心理と半導体株
半導体株は値動きが激しいため、投資家心理を強く揺さぶります。
- 上昇局面:買い遅れる不安(FOMO)
- 下落局面:損切りの葛藤
私はこの心理的負担こそが半導体投資の最大の難点だと思っています。
個別株で勝つには忍耐力と情報収集力が不可欠。
だからこそ、「ETFで淡々と積み立てる」 という戦略を推すのです。
ETFでのアプローチ
米国ETF「SOXX」「SMH」は王道です。
日本では MAXIS 日経半導体株(221A) や NEXT FUNDS 半導体・半導体製造装置35%(346A) なども利用可能です。
私は個人的に、
- 「NISA枠でETF」
- 「余裕資金でNVIDIAや東京エレクトロンを個別株で持つ」
という組み合わせが最もバランスが良いと考えています。
老後資産形成と半導体
「老後2000万円問題」が話題になりましたが、私はむしろ 「インフレで必要額は増えていく」 と考えています。
半導体は長期的に需要が伸びる産業ですから、老後資産形成における「成長の一角」として組み込む価値は大きいです。
ただしポートフォリオ全体を半導体に偏らせるのは危険。
あくまで インデックス投資を土台 に、その上で半導体を「成長ドライバー」として積み増す。
まとめ
半導体は投資テーマとして「王道」と呼ばれるだけの理由があります。
生成AIや自動運転、EV(電気自動車)、IoT、クラウドコンピューティングといった現代の成長分野は、すべて半導体なしでは成立しません。まさに「経済の心臓」とも言える存在です。さらに、米国・日本・EUが巨額の補助金を投じていることからも分かるように、各国が国の安全保障や産業競争力の根幹として位置づけています。
こうした背景を踏まえれば、長期的に半導体需要は右肩上がりであることは疑いようがありません。投資家にとって「外せないテーマ」であることは間違いないでしょう。
しかし、ここで忘れてはいけないのが「半導体株の難しさ」です。私はこれを大きく4つの視点で考えています。
① 循環産業としての宿命
半導体は典型的な循環産業です。需要が急増すると企業は巨額の設備投資を行い、一気に供給能力が拡大します。すると数年後には供給過剰となり、製品価格が暴落する──このサイクルが何十年も繰り返されてきました。特にメモリ市場(DRAMやNAND)はその代表例で、価格は数か月で半分になることも珍しくありません。
投資家にとっては、好況時に買えば天井をつかみ、不況時に怖くなって売れば底で手放すという「逆張りの罠」に陥りやすい分野なのです。だからこそ、半導体株で利益を出すには長期の視点が不可欠だと感じています。
② 技術革新のスピード
半導体は「技術革新が速すぎる」産業です。かつてはインテルがCPU市場を支配していましたが、製造技術の遅れからいまではTSMCに大きく差をつけられています。1980年代に世界を席巻した日本のDRAMメーカーも、いまやシェアを失っています。
つまり、今日の王者が明日の敗者になる可能性が高いのが半導体産業。だから私は「個別株1本に全資産を賭ける」というやり方は極めて危険だと思っています。ETFを活用してセクター全体を押さえるか、複数の有力企業に分散するのが現実的です。
③ 地政学リスクの集中
もうひとつ見逃せないのが「地政学リスク」です。
世界最先端の半導体の多くは台湾TSMCが製造しています。推計によっては先端ノードの6割〜9割を担っているとされるほど。台湾有事が起きれば、世界経済全体に直撃することは避けられません。
このリスクをどう考えるかは投資家にとって難しい課題です。私は「リスクはゼロにできないからこそ、投資比率を調整するしかない」と考えています。半導体に全資産を偏らせるのではなく、インデックス投資や他セクターとの組み合わせで全体を安定させるべきです。
④ 投資家心理の揺さぶり
半導体株は値動きが激しいため、投資家心理を強烈に揺さぶります。
株価が急騰すれば「買い遅れたらどうしよう」という不安(FOMO)が襲い、下落すれば「もうダメだ、売ろうかな」という恐怖に支配される。
私は、この心理的な揺さぶりこそが半導体投資の最大の落とし穴だと考えています。冷静さを保つためには、自分なりのルールを持つことが必要です。私の場合は「基本はETFで積立、個別株は勉強と楽しみの範囲で少額だけ」というルールを守ることで、感情に振り回されないようにしています。
長期投資・老後資産形成との接続
老後2000万円問題が話題になったように、将来の資金準備は誰にとっても避けられない課題です。私は「インフレが進めば2000万円では足りなくなる」と考えています。そのとき、半導体のように成長が見込める産業に投資しておくことは、長期的な資産形成の大きな力になります。
ただし偏重は危険。私は「インデックス投資を土台」にして、その上に半導体ETFを成長ドライバーとして積み増すのがベストだと思っています。これなら安定性と成長性の両方を確保できます。
👉 関連記事:老後2000万円問題はもう古い?インフレ時代の現実と私の考え
私の結論
結局のところ、私はこう考えています。
- 半導体は「投資の王道テーマ」であり、長期で外せない
- しかし短期のボラティリティやリスクも大きく、投資家を翻弄する
- だからこそ、 「インデックス+半導体ETF+少額の個別株」 という組み合わせが現実的で安心できる
半導体は夢のある投資先ですが、それだけに熱くなりすぎるのは危険です。大事なのは「自分がどれくらいリスクを取れるのか」を理解し、その範囲内で参加することだと思います。
投資で一番大切なのは「続けること」。
半導体投資はその刺激的な値動きで多くの投資家を惹きつけますが、最後に勝ち続けるのは冷静に長期戦略を維持できる人だと、私は確信しています。
✅ 関連リンク
- 2026年NISA改正案を徹底解説──「神改正」と呼ばれる理由と投資家が注意すべき3つの落とし穴
- 老後2000万円問題はもう古い?インフレ時代の現実と私の考え
- インデックス投資は最強の資産形成術?初心者にもおすすめの理由
✅ 参考リンク
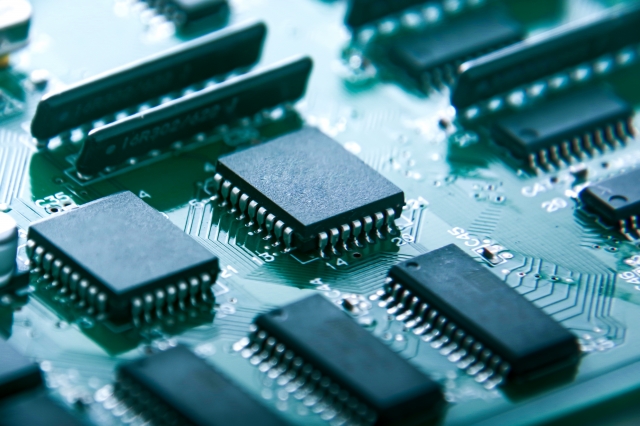




コメント